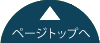河本顧問によるレクチャー①「地球・日本列島の営みとしての地震」
河本顧問は30年にわたり、地球の営みを学び伝えようとしてきました。それをベースに春は地震をテーマに、秋は中央構造線をテーマにお話しします。
できるだけていねいに、事前に内容をホームページに載せて、サブテーマごとにQ and Aを設けながらお話しするつもりです。当日は時間の関係でサブテーマの一部割愛するかもしれませんが、ご質問はお受けします。途中参加可能、出入り自由とします。
日時
2025年5月11日(日) 10時~15時(16時まで延長する可能性有)
開催場所
大鹿村交流センター ホール
※人数次第で部屋が変更となる可能性があります。
申込先
人数把握のため、お手数ですが、参加予定者はお電話、もしくは問い合わせフォームから事前申込をお願いします。
■お電話での申込先: 0265-39-2205 大鹿村中央構造線博物館
■問い合わせフォームはこちら
題名に「河本顧問レクチャー申込」とご記入ください。メッセージ本文に、参加人数をご記入ください。
※参加可否が直前まで決まらない方も、「参加可能性有」ということで、事前申し込みにご協力お願いいたします。その場合、キャンセルのご連絡は不要です。
申込締切
2025年5月4日(日)
備考
- 昼食持参を推奨いたします。食事しながら河本顧問との交流が可能です。
- 参加費は無料です。
主催
大鹿村中央構造線博物館
共催
大鹿村公民館
プログラム
地球・日本列島の営みとしての地震
5月11日午前10:00~12:00 第1部と第2部
第1部 海洋プレート沈み込み帯にある日本列島
1-1,地球は何でできている?
中心核・マントル・地殻。
とても重い鉄とニッケルの中心核(内核は固体、外核は液体)。
重いかんらん岩成分のマントル(固体)。
やや重い玄武岩質の海洋地殻と大陸下部地殻、軽い花崗岩質の大陸上部地殻。
下に重いもの、上に軽いものが重なっている。
1-2,地球の温度(地温)
中心は熱く表面は冷たい
地球が誕生した時には星屑が中心に集まっていき発熱。
その余熱が残り、中心の推定温度6000℃。
地球表面は宇宙に熱が逃げて冷たい。平均15℃。
冷えると重くなるので、上が冷たく下が熱い状態は不安定。
核とマントルは重さが大きく異なるので混ざらない。
マントルの中では、上部の冷えて重くなったマントルが下に沈んでいく。
1-3,マントルの性質
固体だが最上部を除き高温で流動的。
マントルの温度は、深部ほど高い。2900㎞下の底の推定温度3000~4000℃。
マントルかんらん岩の融点は、圧力が高い深部ほど高くなる。
深部に向かって地温が上がるが圧力も上がるので、マントルは固体。
固体だが、高温のマントルかんらん岩は、壊れずにゆっくりと変形できる。
ひじょうにゆっくりだが、互いに位置を変えられるので「流動的」と言う。
(マントル上部では一部が融けてマグマができますが、その話は秋にやります)
1-4,プレートとは何?
マントル最上部の厚さ100㎞以下の低温で固いマントルと薄い地殻の部分。
地球の表面に近い浅いマントルは1000℃以下に冷えて固い。
流動性を失って板のようになったマントルがプレートの本体。
したがって「プレート」とは物ではなく状態。
プレートは何枚かに割れている。一体に動いている1枚をプレートという。
1-5,海洋プレートと大陸プレート
海洋プレートは、重い海洋地殻を載せたプレート。
大陸プレートは、軽い大陸上部地殻と重い大陸下部地殻を載せたプレート。
海洋プレート部分と大陸プレート部分が一体になっているプレートもある。
たとえば北アメリカプレート、インド‐オーストラリアプレートなど。
フィリピン海プレートも伊豆‐小笠原列島は大陸地殻に相当。
(異なるマグマ活動で海洋地殻と大陸地殻が造られますが、その話は秋に)
1-6,プレートの運動はどうして起こる?
冷えて重くなった海洋プレートが一方の端から地球内部に沈み込んでいく。
沈み込んでいる場所には海溝ができる。
海洋プレートは、この一端からの沈み込みに引かれてプレート全体が移動する。
軽い大陸上部地殻を載せた大陸プレートは沈まない。
1-7,離れていくプレート同士の隙間にできる中央海嶺
2枚の海洋プレートが反対方向に移動すると隙間ができる。
隙間にはすぐ下から温かく流動的なマントルが上昇し、中央海嶺になる。
上昇した温かいマントルは冷えてプレートになっていく。
移動する海洋プレートは、さらに冷えて厚く重くなっていく。
1-8,沈み込んだ海洋プレートの行方
日本海溝から沈み込んだ太平洋プレートは、ロシアや中国の下で深さ660㎞に。
そこまでは固いプレート状態で、プレート内の地震を起こしながら沈んでいく。
そこからは流動的だが周囲より冷たく重いマントルの下降流になる
(コールドプリューム)
1-9,海洋プレートの沈み込みが、沈み込まれる側に大きな変動を起こす
マリアナ型沈み込みによる引き出し。
マリアナ海溝は中央海嶺から遠く、よく冷えた太平洋プレートが高角度で沈み込み。
マリアナ海溝は後退し、マリアナ諸島が引き出され、背後にマリアナトラフが拡大。
日本では、琉球海溝がマリアナ型。
南九州‐南西諸島が引き出され、背後に別府‐島原地溝帯と沖縄トラフが拡大。
チリ型沈み込みによる押し込み。沈み込まれる側の下に浅いプレート境界。
チリ海溝は中央海嶺から近く、あまり冷えないナスカプレートが低角度で沈み込み。
日本では南海トラフがチリ型。
Q and A
1-10,日本列島でも、海溝側への引き出しと地殻が引き延ばされた時代があった。
2000万年前~1500万年前の日本列島が大陸から離れた大変動。
太平洋プレートが沈み込む千島海溝・日本海溝・伊豆‐マリアナ海溝が後退。
千島列島、大陸の一部だった東北日本と西南日本、伊豆‐マリアナ列島が引き出され。
背後の千島海盆・日本海盆・大和海盆・四国海盆・パレスベラ海盆がそれぞれ拡大。
とくに東北日本には、地殻の引き延ばしによる多数の正断層と地溝が発達した。
1-11,1500万年前に日本海の拡大が終了
1-12,西南日本へのフィリピン海プレートの沈み込みの始まり
1500万年前までには、伊豆‐小笠原海溝の東進により、西南日本に沈み込む海洋プレートはそれまでの太平洋プレートからフィリピン海プレートに変わった。
拡大したばかりの若いフィリピン海プレートが低角度のチリ型で沈み込んでいる。
西南日本の下のプレート境界は、東北日本のそれより浅い。
1-13,伊豆‐小笠原列島の多重衝突の始まり
1500万年前ごろから古伊豆‐小笠原列島の北上と衝突が始まった。
櫛形・御坂・丹沢・伊豆地塊が次々と衝突。
衝突した地塊は、衝突後はユーラシアプレートの一部になった。
その南縁にプレート境界が移動し、次の地塊の衝突が始まる。
プレート境界は最初の櫛形地塊西縁から丹沢地塊北縁さらに伊豆地塊北縁へ移った。
1-14,300万年前以降、現在の日本列島の変動が始まる
1-15,日本海溝の西進が始まり、日本列島の大部分は東西圧縮の場になった。
1995年兵庫県南部地震(逆断層成分をもつ右横ずれ断層)
昔の東西伸長による正断層の古傷は、東西圧縮により逆断層の活断層になっている。
正断層から逆断層にずれ方が逆転したので「逆転(インバージョン)」呼ばれている。
2003年宮城県北部地震、2004年新潟県中越地震、2008年岩手宮城内陸地震。
2014年長野県神城断層地震、2024年能登半島地震。
1-16,フィリピン海プレートの進行方向が北西向きに変化
南海トラフの四国沖から沈み込む区間では海溝に対して斜めに沈み込むようになった。
そのため南四国が西向に引きずられるようになった。
中央構造線の古傷の四国‐紀伊半島東部の区間が右横ずれの活断層になった。
1-17,南北の引っ張りによる沖縄トラフ・別府‐島原地溝帯の拡大
琉球海溝ではフィリピン海プレートの古い部分が高角度で沈み込むマリアナ型。
南九州‐南西諸島が引き出され、背後の別府‐島原地溝帯と沖縄トラフが拡大。
そのため中部九州は現在の日本列島では例外的に南北伸長の場になっている。
2016年熊本地震(正断層成分を持つ右横ずれ断層)
Q and A
1-18,プレート境界も移動する
プレートは一体に運動している1枚
あるプレートの一部が離れ、別のプレートの一部になることがある。
1-19,伊豆‐小笠原列島の衝突境界の移動
現在のフィリピン海プレート上の伊豆‐小笠原列島とユーラシアプレートの本州との衝突境界は伊豆地塊北縁。
将来は伊豆半島南縁へ移り、神津島‐銭洲海嶺が衝突すると考えられている。
1-20,東北日本の帰属をめぐる議論
日本海盆の拡大の結果、東北日本はアムールプレート(広義の区分ではユーラシアプレート)と独立した運動をするマイクロプレートになったという見方がある。
さらにオホーツクプレート(広義の区分では北アメリカプレート)に属する北海道東部と合体し、北アメリカプレートの一部になったという見方がある。
この見方は1983年日本海中部地震がプレート境界型とされ裏付けられたとされた。
しかし、最近は日本海中部地震も他の東北地方の地殻内の地震という見方が有力。
「4枚のプレートがひしめく日本列島」は過大?
「2枚の海洋プレートが沈み込んでいる日本列島」はまちがいない。
その影響が最も現れているのが関東地方。
Q and A
1-21,現在の日本列島付近で起こる地震
プレート境界型地震、沈み込む海洋プレート内地震、日本列島の地殻内地震
(午後にお話しします)
第2部 地震はどのように発生する?
2-1,震源断層
地震の発生源は地下の固い岩盤に生じる瞬間的なずれ動き。
ずれ動きに伴って地震波が生じる。
地震の発生源になったずれ動きが生じた食い違い面を、その地震の震源断層という。
2-2,震源断層はなぜずれる?
岩盤に圧縮や伸長がかかり続けることで、ひずみ(変形)が増大。
ついにひずみが岩盤が耐えられる強度を超えると、一気に破壊してずれ動く。
ずれ動きによりひずみは解消し、断層のずれ動きは止まって固着する。
同じ向きの圧縮や伸長がかかり続けることで再びひずみの蓄積と破壊を繰り返す。
2-3,震源断層は力の向きにたいし斜めに生じる
断層面の向きとずれ方
正断層;水平な引っ張りにより重力の向きにたいし斜めにずり落ちる断層。
逆断層:水平な圧縮力により縦方向に斜めにせりあがる断層。
右横ずれ断層:相手側が右横方向にずれる断層。
左横ずれ断層:相手側が左横方向にずれる断層。
2-4,震源って何?
震源断層は面積がある。その中で最初にずれ動きが始まった点が震源。
2-5,マグニチュード
地震発生源の規模の大小を「地震のマグニチュード」で表す。
地震のマグニチュードと震源断層の面積は密接に関連。
マグニチュード9.0の地震の震源断層の面積は巨大。150㎞×450km以上。
2-6,震源断層内のずれ破壊の場所の移動
ずれ動きそのものの速度は人が走るぐらい。
震源断層内のずれ破壊の場所はジェット機並みのスピードで移動する。
2-7,アスペリティ(特に強い地震波を出した領域)。
震源断層内のすべての場所からずれ破壊にともない地震波が発生する。
震源はずれ動きが始まった点。震源からとくに強い地震波が出るわけではない。
震源断層内で特に強い地震波を発生した領域をアスペリティという。
2-8,モーメントマグニチュードと気象庁マグニチュード
地震で震源断層から解放されたエネルギーをモーメントマグニチュード(Mo)で表す。
日本では測り方が異なる気象庁マグニチュード(Mj)が使われてきた。
1995年兵庫県南部地震のMjは7.3、Moは6.9。
Q and A
2―10,縦波(P波)と横波(S波)
震源断層のずれ動きで縦波(P波)と横波(S波)が発生する。
縦波は圧縮と膨張のくりかえしによる振動で、波の進行方向に振動する波。
横波はばねをはじくような振動で、波の進行方向に直交する向きに振動する波。
2―11、地震波が進む速度
縦波は速く、横波はゆっくり伝わる。地表面には縦波が最初に到達するのでPrimary wave(P波)、横波は遅れて到達するのでSecondary wave(S波)という。固い地殻の上部でP波は秒速5km、S波は秒速3km。やわらかい堆積層では地震波の進行速度が遅くなるかわり振幅は増幅される。
2―12,初動時刻
震源から発生した地震波が地表面に到達すると地面が揺れ始める。
揺れが観測された時刻を初動時刻という。
震源から遠いほど、初動時刻は遅くなる。
2―13,初期微動継続時間
P波による地面の揺れは弱く初期微動という。
遅いS波が到達するまでの時間は、震源が遠いほど長くなる。
初期微動継続時間1秒につき震源との距離はおよそ8㎞。
浅い震源断層の直上ではP波とSの時間差がほとんどない。
遠方では初期微動が弱すぎて人体に感じられないこともある。
2―14,震度
地震波の到達によって生じる地面の揺れの強弱を「震度」で表す。
地面の揺れを感じて「地震だ」と気づくが、地震の発生源は別の場所の地下にある。
Q and A
2―15,地殻変動
震源断層のずれ動きによって、地表面に隆起や沈降などの地殻変動が生じる。
2-16,津波
海底面に大きな隆起や沈降が生じると、その上の海水に津波が生じる。
ゆれではなく海底の上下変動で海水が持ち上げられたり引き下げられたりして 生じる。
2-17,地表地震断層
震源断層が浅く、マグニチュードが大きい(震源断層の面積が広い)とき、震源断層の上端が地表に達して地表面に食い違いが生じることがある。
おもに日本列島の地殻内の地震にともなう場合に使われる。
地表地震断層が出現すると、その真上にまたがって建っている構造物が被害をまぬがれることはきわめて難しい。
2-20,震災
震災は地震災害のこと。自然現象の地震の名前のほかに震災名がつけられることがある。
1923年関東地震の災害は関東大震災。1995年兵庫県南部地震の災害は阪神淡路大震災、2011年東北地方太平洋沖地震の災害は東日本大震災と呼ばれる。
自然現象の要素であるマグニチュードや震度について、「東日本大震災のマグニチュード」「阪神淡路大震災の震度」などの言い方は誤った使い方になる。
Q and A
5月11日午後13:00~15:00 第3部と第4部、QandAが残る場合、16:00まで延長可。
第3部 日本列島付近で起こる地震
3―1,プレート境界型地震
沈み込んだ海洋プレートと大陸プレートがかみ合っている領域が震源断層になる地震。
太平洋プレートでは深さ50㎞まで、フィリピン海プレートでは深さ35㎞まで.
この固着域では、海洋プレートの沈み込みによってひずみが蓄積していく。
それより深いプレート境界は、海洋プレートから出てくる水で滑りやすくなることや、温度が高く岩石がゆっくり変形できるようになるため。ゆっくり滑っていて、地震を起こすひずみは蓄積しないと考えられている。
なお海溝から深さ10㎞までの間は、水を含んだ柔らかい堆積物のため滑りやすく、強い地震波は発生しないと考えられている。
3―2,プレート境界型地震の規模
海溝から固着域の深い側までの幅は200㎞もあり、この幅の全体が海溝と平行の長さで500㎞ほど動くと、マグニチュード9.0の超巨大地震になる。
その3割の面積が3分の1の滑り量だけ動いても、マグニチュード8.0の巨大地震になる。(エネルギーが30分の1,マグニチュードが1つ小さい)
3-3,南海トラフ巨大地震(マグニチュード9.0)の震源域って何のこと?
このマップは良く目にする。2次元の地図なので深さ方向は読み取れないが、図で囲まれた範囲は地下のプレート境界の固着域の範囲を表している。内陸側の境界線の宮崎~松山~徳島~有田~亀山~四日市~名古屋港~豊田~飯田市竜東~大鹿~甲府盆地は、深さ35㎞の固着域の深い側の境界になっている。
したがってマグニチュード9.0の南海トラフ巨大地震が発生するときには、この領域の地下のプレート境界の全面積がずれ動き、全面積から地震波が放出される。
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku/pdf/1_1.pdf
南海トラフから深さ10㎞までの領域は強い地震波は出さないが、海底の大きな隆起が生じるため大津波の発生域(津波の波源域)になる。
3-4,プレート境界型地震の再来間隔
日本海溝から沈み込んでいる太平洋プレートの速度は約10㎝/年、南海トラフから沈み込んでいるフィリピン海プレートの速度は5㎝/年なので、プレート境界の固着域にはひじょうに速くひずみが蓄積する。そのためマグニチュード8程度の地震は100年~200年おき、マグニチュード9程度の地震は1000年おきという短い間隔で発生する。
3-5,古文書に残る再来間隔
南海トラフ巨大地震の震源域で発生したマグニチュード8級の巨大地震の記録は飛鳥時代までさかのぼる。マグニチュード8級の巨大地震は平均150年おきにくりかえし発生している。
最新の発生は、駿河湾から沈み込む領域で1854年。遠州灘~熊野灘から沈み込む領域で1944年。土佐沖から沈み込む領域で1946年。
3-6,半割れケースとは?
南海トラフ巨大地震の震源域ではその半分の領域が震源断層のマグニチュード8級の地震が発生し、短い間をおいて残りの領域でマグニチュード8級の地震が発生する例があり、半割れの連動とされる。
1854年12月23日に固着域の東半分が震源断層になった安政東海地震が発生し、30時間後の12月24日に西半分が震源断層の安政南海地震が発生した。
1944年12月7日には東半分の遠州灘以西が震源断層になった昭和東南海地震が発生し、2年後の1946年12月21日には西半分が震源断層の昭和南海地震が発生した。ただし最東部の駿河湾から沈み込んでいる部分は1944にはずれ動いていない。
この半割れケースが起こった場合、残りの半分の避難をどうするかが課題になっている。
3-7,南海トラフ巨大地震と2011年東北沖地震の揺れの比較
太平洋プレートは日本海溝から高角度で沈み込んでいるので、2011年東北沖地震の震源断層の深い側(深さ50㎞)も陸域の下まで達していない。
南海トラフから沈み込むフィリピン海プレートはチリ型で、陸域の下に浅く広く沈み込んでいる。南海トラフ巨大地震の震源断層の面積の約4割は陸域の下に広がり、しかも浅い。
したがって南海トラフ巨大地震の陸域の揺れは、2011年東北沖地震の揺れよりはるかに強い。マグニチュード8級の半割れでも発生した側でははるかに強い揺れになる。
3-8,南海トラフ巨大地震と2011年東北沖地震の津波の比較
プレート境界型地震の場合、海溝付近の地殻変動が津波の発生源になる。
日本海溝と海岸の距離が遠い東北沖では、本震から津波の到達まで30分かかった。
南海トラフと陸域が近い西南日本では、津波はもっと早く到達する。特に御前崎、潮岬、室戸岬には、本震発生後数分以内に津波が到達すると考えられている。
Q and A
3-9,沈み込む直前の海洋プレートの内部で起きる地震
海洋プレートは変形しながら沈み込んでいる。
海溝の沖側では、海洋プレートは下方へ大きく曲がり始める。折れ曲がり部分にはアウターライズという盛り上がりができたり、割れ目がずり落ちる正断層ができる。
この折れ曲がりに伴う地震は、海溝よりさらに沖合の遠方で発生するため、陸地に伝わる地震波は減衰して強い揺れを感じない。しかし海底に大きな地殻変動を生じるため大きな津波を発生する。
1896年明治三陸津波地震は揺れが弱いために無警戒だったところに大きな津波が来たために大きな災害になったが、このタイプの地震だったと考えられている。
3-10,沈み込んだ後の海洋プレートの内部で起きる地震
プレート境界面より下の海洋プレートの内部では、沈み込みにともなって頻繁に地震が発生している。
東北・関東・中部地方の地下深部では沈み込んだ太平洋プレートの内部で地震が発生。
四国・瀬戸内海の地下深部では沈み込んだフィリピン海プレートの内部で地震が発生。
2924年4月17日に愛媛県宇和島付近の地下39㎞が震源の気象庁マグニチュード6.6の地震はフィリピン海プレートの内部で発生した地震で、南海トラフ巨大地震を起こすプレート境界の地震ではない。この付近のプレート境界の深さは約30㎞なので、震源の深さに注目すると区別できる。
一方、2024年8月8日の日向灘の地下31㎞が震源の気象庁マグニチュード7.1の地震はプレート境界で発生した地震だった。より東方のプレート境界の地震に連動する可能性がないとは言えなかった。
3-11,ロシアのハバロフスクの地下700㎞付近で発生する地震
沈み込んだ太平洋プレートの内部ではハバロフスクの地下まで地震を発生する。固い太平洋プレートの内部を地震波が伝わり、ロシアよりも日本の方が強い揺れを感じることがある。
Q and A
3-13,日本列島の地殻で発生する地震
300万年前ごろに始まった日本海溝の西進により、現在の日本列島の北海道西部~北九州の地殻は東西に圧縮されている。
東西圧縮により生じる断層は、南北方向の断層は押しかぶさる逆断層、北西‐南北方向の断層は左横ずれ、北東‐南西方向の断層は右横ずれになる。
3-14,地殻内地震の震源断層の深さ
日本列島の地殻の厚さは30㎞~50㎞程度だが、深さに応じて地温が上がり深さ15㎞で300℃以上になる。
上部地殻の花崗岩は300℃を超えるとゆっくり変形できるようになる。
そのため、深さ15㎞ないし20㎞より下では、地殻内地震は発生しない。
したがって、震源の深さに注目すると、地殻内地震かプレート境界型か、沈み込んだ海洋プレート内の地震か区別できる。
3-15,地表地震断層の出現
マグニチュードが7.0の震源断層の幅は20㎞ていどになる。
地殻内地震が発生する深さ方向の幅(地表~最深部)は20㎞より狭い。
そのため震源断層の上端が地表にまで達して、地表面に食い違いが生じる。
3-16,震源断層の長さと地表地震断層の長さ
マグニチュードが6.5~7.2程度の地殻内地震では震源断層の長さの一部が地表に出現。
マグニチュードが8.0の地殻内地震では震源断層の長さの全長が地表に出現。
Q and A
3-17,活断層
地表地震断層による地表の食い違いが浸食や埋積で失われずに残り、ふたたび地表地震断層が出現すると、地形の食い違いが成長する。
この食い違いを活断層という。
同じ向きの力が地殻に加わり続けると、地震断層の弱面が再び地震断層になると考えられるので、活断層の地下で再び地震が発生し、規模が大きいときは活断層の位置にふたたび地表地震断層が出現すると考えられる。
ただし。自然現象の揺らぎと、人間側の推定位置の誤差で、将来の地表地震断層の位置を数10m以内というような高い精度で推定するのは難しい。
3-18,活断層の活動間隔
活断層の発掘調査などで、そこにずれ動きが繰り返された(くりかえし地表地震断層が出現した)ことが分かる場合、活断層の活動間隔という。
活断層の活動間隔は数百年~数万年なので、歴史記録に残ることはまれで。活断層が切っている地層の年代から推定される。
3-19,活断層の変位量
一方、最長の活動間隔を超える数万年以上の長期間に、活断層の食い違いがくりかえされることによって生じた地形面の食い違いは、数万年以上前の地層や地形面が現在どのぐらい食い違っているかにより知ることができる。
3-20,活断層の活動度
この長期間の食い違い量から求められる長期間の食い違い速度を活断度という。
ふつうは1000年または1年単位で表す。
これは将来のずれ動き量がどれぐらいの速さで貯まっているかと考えることもできる。
A級:1m~10m/1000年または1mm~10mm/年
B級:0.1m~1m/1000年または0.1mm~1mm/年
C級:0.01m~0.1m/1000年または0.01mm~0.1mm/年
3-21,C級活断層問題
活動度が高い活断層ほど活動間隔や1回のずれの量、最新活動年代などが得られやすい。
逆にC級活断層では、これらのデータを得ることが難しい。
さらに、活動間隔が長いC級では、次のずれ動きが出現する前に浸食や埋積により痕跡が消えてしまい発見できないのではないかという考えがある。
知られている活断層のずれを合計しても、測量による日本列島の地殻の変形量の1割程度にしかならないことが、多数の未発見のC級活断層があるのではないかと考えられた。
一方、日本列島の上部地殻にも、活断層を生じないゆっくりとした変形があるのではないかという見方もある。
Q and A
3-22,現在の日本列島の造山地・造盆地運動
現在の日本列島の上部地殻は、圧縮を受けて薄氷を割るようにブロック化し、傾いたり回転したり押しかぶさったり横ずれし、山地と盆地・平野の大きな地形を作っている。
ブロック(地塊)の境界は活動度が高い活断層で区切られている。
3-23,活断層の向きとずれ方から推定できる地殻の約300万年前以降の東西圧縮
東北地方・中部近畿地方。北九州の活断層から東西圧縮が読み取れる。
南北方向の活断層は逆断層、北西‐南東方向の活断層は左横ずれ、北東‐南西方向の活断層は右横ずれになっている。
これは明治からの三角測量や30年間の衛星測量とも一致する。
3-24,赤石傾動地塊と木曽山脈の地塊、伊那谷断層帯
赤石傾動地塊は諏訪湖を頂点とし、天竜川と富士川を2辺とする三角形の地塊で、西へ傾きながら隆起している。東縁では糸魚川‐静岡構造線(活)断層帯で甲府盆地の地塊に押しかぶさり、西縁では伊那谷断層帯で木曽山脈地塊が押しかぶさっている。木曽山脈地塊の西縁は上松断層などで阿寺山地の地塊に押しかぶさっている。
3-25,濃尾傾動地塊
濃尾傾動地塊は東側が上昇し西側が沈降する傾動地塊。東縁は猿投‐高浜断層で猿投山~知多半島側が隆起。西縁は養老断層で養老山地が押しかぶさっている。濃尾傾動地塊の養老断層沿いが最も沈降量が大きく、1800mに達し、揖斐川・長良川・木曽川の三川がそこに向かって流れも移籍して濃尾平野を造っている。
3-26,近畿トライアングル
敦賀付近を頂点に、養老断層~伊勢湾を1辺、花折断層~六甲‐淡路断層を1辺、中央構造線を南縁とする三角形の地帯は近畿トライアングルと呼ばれ、変動地塊と活断層により山地と盆地・平野が造られている様子が分かりやすい。
関西では、山地に日本列島の土台になっている大陸だった時代の岩石が露出して、山地の縁に活断層がよく露出している。
3-27,活断層と地震
活断層は地表地震断層が繰り返し出現した跡だから、地表にずれが達しないマグニチュード6.5以下の地震は活断層に痕跡を残さずに発生してきたと考えられる。
逆に活断層の活動間隔とは、地表地震断層が出現する、おおむねマグニチュード7級の地震の繰り返し間隔を示している。
地表の活断層の地下部分で、マグニチュード6.5以下の地震はもっと短期間で発生すると考えられる。
3-29,活断層の活動の再来間隔
A級活断層でも大地震を起こすのは数百年~数千年おきなので、歴史記録に残っても1回で、全く記録が見られないほうが多い。
発掘などによるデータを合わせても、かなりの精度で再来間隔が推定できて最新活動の年代も推定できているは、松本~諏訪の糸魚川‐静岡構造線(活)断層帯だけではないかと思う。
松本~諏訪の糸魚川‐静岡構造線(活)断層帯は諏訪盆地を造っている活断層で、再来間隔は約1000年、最新の活動は762年の信濃の大地震と考えられている。
Q and A
3-30,地震の発生源ごとの地表の揺れの評価
それぞれのプレート境界型地震や活断層の地下から発生する地震について、震源断層モデルが作れれば、そこで発生する地震波と地下の岩盤中の伝わり方を設定し、地面の揺れの強弱の分布を計算できる。
これにより、そこからいつか必ず発生する地震による揺れの強弱の予測はできていることになる。しかし、いつ発生するかという予測は含まれない。
3-31,地震の発生源ごとの発生確率評価
それぞれのプレート境界型地震と、かなりのデータが得られている活断層については、再来間隔と最新活動年から、今後30年以内の発生確率が求められている。
再来間隔3000年の地震が30年以内に発生する確率は1%だから。30年確率が1%を超えたらその地震の発生に向かって道半ばを越えたと考えることができる。
歴史記録が残り、再来間隔が短い西南日本のプレート境界型地震については、確率が高いと同時に信頼性も高いといえる。
3-32,確率評価は地震発生の順番を意味しない
1万年おきに地震を発生する断層が30年以内に地震を発生する確率は、100年おきに地震を発生する断層が30年以内に地震を発生する確率より圧倒的に低い。
しかし1万年おきに地震を発生する断層でも、ひずみが蓄積されれば地震を起こす。今が1万年目であれば地震を起こすので、確率が高い断層から順番に地震を起こすのではないことに注意。
3-33,地表の地点ごとの揺れ(地震動)の確率評価
ある地点に注目し、それぞれの震源断層の地震による揺れの強さと確率を足し合わせると、その地点が今後30年以内に揺れる強さごとの確率が得られる。これには未知の断層による地震による揺れもバックグラウンドとして加えられている。
東北日本や西南日本の太平洋側ではプレート境界型地震の確率が高いので、ほとんどがプレート境界型地震による揺れで塗りつぶされてしまう。が示されている。直下の活断層による揺れは強いが確率が低いので、図には反映されにくい。
日本海側ではプレート境界型地震による揺れが弱いので、活断層からの揺れの影響が読み取れる。ただし能登半島沖の海底活断層については評価が間に合わなかった。
糸魚川‐静岡構造線(活)断層帯は活断層としては高い確率が分かっているので、マップに反映されている。
Q and A
第4部 中央構造線や糸魚川‐静岡構造線などの古傷と活断層の関係
4-1,過去の変動と現在の変動
日本列島の土台は、およそ3億年前の古生代の終わりごろから古アジア大陸に海洋プレートが沈み込む沈み込み帯で造られてきた。
大陸から離れたのは、現在の哺乳類が大繁栄を始めた新生代新第三紀の2000万年前から1500万年にかけての変動で。大陸時代に造られた地質帯は土台になっている。この変動も終わっている。
今の日本列島の起伏を造っているのは第四紀の約250万年前~現在進行中の変動による。
4-2,地質断層
日本列島の土台には、過去の変動によって生じた断層(食い違い面)が無数にある。
断層は力の向きにたいし斜めに生じる。断層をくりかえしずれ動かした変動期が終わり、力の向きが変わればその断層はもはや動かず、地質の食い違い面として痕跡が残るだけになる。
かつてずれ動いたことで生じた地形の食い違いも、浸食や埋席で失われ、断層は地質中の食い違いとして残るだけになり、地質断層と呼ばれる。。
大規模な地質断層では、大きな食い違いのために、例えば浅いところに堆積した地層と深いところにあった地層とか、熱いところで造られた岩石と冷たいところで造られた岩石とか、由来の異なる岩石同士が接する地質境界になっている。
地質境界になっている大規模な地質断層でも、過去の変動で生じたもので、現在の変動とは関係がない。
例えば中央構造線は大陸だった中生代白亜紀の岩石どうしの地質境界で、両者を接しさせた活動も大陸だった時代に生じた。
4-3,再活動
昔の古傷も、のちの時代の変動で生じる力の向きにとって、都合の良い向きにあれば利用される。ただしずれ方が同じになるとは限らない。
たとえば糸魚川‐静岡構造線北部は、2000万年前から1500万年前の日本列島が大陸から離れた変動期に、本州の折れ目になって東西に引っ張られて追い込んだ北部フォッサマグナ地域の西縁に生じた断層で、フォッサマグナ側がずり落ちる正断層として生じた。
その古傷の断層面は、300万年前から始まった東西圧縮に利用され、逆転してフォッサマグナ側が松本盆地に押しかぶさる逆断層の活断層になっている。
4-4,中央構造線
中央構造線の中部~関東の区間は、西南日本にフィリピン海プレートが沈み込み始めて伊豆‐小笠原列島の衝突が始まった1500万年前ごろに大きな変動を受けた。
中部地方では櫛形地塊の衝突を受けて北方に大きく曲げられ、断層面も立ち上がって垂直に近くなり、さらに南東からの力で新しく生じた赤石構造線とつながって60㎞の左横ずれが生じた。
これによって四国~紀伊半島の中央構造線とは向きが異なる断層になった。
関東でも北向きに曲げられ北東‐南西方向の断層になった。
4-5,中央構造線を利用した活断層
現在は中央構造線は四国、中部、関東で全く向きが異なる別々の断層になっている。
一方、日本列島の現在の変動は、九州は南北の引っ張り、四国~紀伊半島西部は北西方向の押しによる引きずり、中部地方は東西圧縮、関東山地はおそらく南西からの押しになっている。
この関係で古傷が最も利用されているのは四国~紀伊半島西の区間で、A級の右横ずれ活断層になっている。
紀伊半島東部ではおそらく活断層ではないが、伊勢平野南縁~豊川の区間は不明。
赤石地塊の内部の区間は、南北方向で垂直の断層面で東西圧縮で動きにくく、C級の右横ずれ活断層になっている。この地域の大地形を造っている主要な活断層は、A~B級の伊那谷断層帯で、伊那盆地を造っている。
九州では阿曽算に覆われて、中央構造線の位置も未解決、関東では関東平野の3000mの堆積物に覆われて詳細は分からない。
4-6,「構造線」の名に引きずられずに、活断層として評価
このように地質断層としての構造線は、現在は地域により向きも異なり力の受け方も異なっている。
活断層かどうかは、最近の時代の地形や地層を食い違わせているかどうかで判定する。地震を考えるときには、シンプルに活断層としての判定と評価だけをすべきと考えます。
河本顧問略歴
大鹿村中央構造線博物館顧問・非常勤学芸員。
1951年東京生まれ。放送大学卒。
常勤退職まで、日本地質学会・日本地震学会員、現在は日本活断層学会のみ所属。